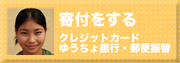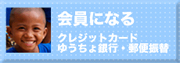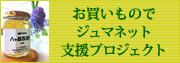ジュマ・ネットの新ホームページが開設いたしました!
デザインを一新し、温かみのあるホームページへと切り替わりました。
以下のアドレスからご覧ください。
https://donate.jummanet.org/
また、マンスリーサポーターも現在募集中です。
今後もジュマ・ネットへのご支援ご協力お願いいたします。
- 2021/12/30
- アーユスNGO大賞受賞記念講演会【開催決定!】
- 2021/12/16
- 下澤共同代表がNGO大賞を受賞しました!
- 2021/10/13
- 新ホームページが開設しました!
- 2021/05/15
- インド、アッサム州で国籍を奪われた人々のためのプロジェクト 進捗状況です
- 2021/01/13
- インド・アッサムで動きだしたプロジェクト(会報記事をお届けします)
- 2020/12/02
- ソーシャル・ジャスティス基金 助成発表フォーラムのお知らせ
- 2020/12/01
- インド、アッサム州で何がおきているか 会報の記事をお送りします
- 2020/07/14
- 2020年4月号掲載のチッタゴン丘陵の最新情報です
- 2019/04/06
- ジュマ・ボイサビ・ジャパン2019の開催について
- 2019/03/23
- チッタゴン丘陵とロヒンギャ難民問題 4つの懸念