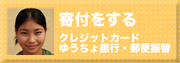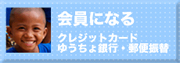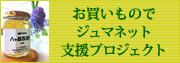チッタゴン丘陵委員会(CHT委員会)の再結成

80年代後半に欧米の人権活動家たちによって設立されたCHT委員会(CHT
Commission)はエルシャド政権が倒れた直後で混乱していた1990年にチッタゴン丘陵とトリプラ州の難民キャンプを訪問、軍の監視を受けずに調査を行い、"Life
is Not Ours"(人生はわがものにあらず)と題する画期的な報告書で世界にチッタゴン丘陵の問題を知らせた。これは、特にヨーロッパでジュマ支援運動の原動力となり、和平協定調印への機運も高めた。しかし、CHT委員会は2001年に4回目のアップデート報告を出した後、ジュマ内紛などで国際社会の関与の糸口が見えず、長らく活動が停止していた。
2006年春にジュマ・ネット代表、下澤さんがヨーロッパ各国を回り、CHT委員会で中心的な役目を果たしたデンマークのNGO、IWGIA(先住民族問題国際作業グループ)やオランダのOCCHTC(CHTキャンペーン組織化委員会)などを訪問した。和平協定が調印されて10年経っても、まともに実施されず、状況が改善していないため国際的に連携した取り組みを再開する必要があるという危機感を共有した。その後も話し合いが進められ、デンマークに事務所をおくIWGIAを中心にCHT委員会を再結成する動きが始まり、ジュマ・ネットもCHT委員会の3ヵ年活動を一部資金支援することになった。
そして2008年5月31日~6月1日にコペンハーゲンで会議が行われ、新しい顔ぶれのCHT委員会が正式に再結成された。新たにバングラデシュ国内のNGOや研究者、弁護士らも加わることになった。英国上院議員として長年CHT問題に関わってきたエリック・エーブブリー氏、バングラデシュ国内でCHTでの襲撃事件の調査などに取り組んできたスルタナ・カマル氏、文化人類学者のアイダ・ニコライセン氏の3人が共同代表に選ばれ、世界的に著名な先住民族問題専門家・人権活動家たちが委員として勢ぞろいした。日本からはアイヌ民族や沖縄の人々と共に国連で活動して来られた上村英明さんが委員に加わることとなった。
■プロジェクトの概要
|
プロジェクト最終責任者 |
|
|
プロジェクト実施者 |
OCCHTC、IWGIA、Jumma Net Japan |
|
総予算 |
412,474 EUR(3,101,986 DKK)(3ヵ年合計 約6,723万円) |
|
プロジェクト期間 |
3年(2008年1月~2010年12月) |
|
活動計画 |
|
|
A.定期的なバングラデシュ訪問 |
第1回は2008年の2月か3月に実施。その後は、2008年11月、2009年8月、2010年2月に正式訪問を検討する。また、必要に応じて緊急事実確認訪問を行なう。 |
|
B.出版 |
和平協定の実施状況のスタディ、人権侵害に関する定期的な報告書作成、フォローアップレポート(2008年、2009年、2010年) |
|
C.市民の気づきとメディアキャンペーン |
ハガキキャンペーン、国際セミナーやシンポジウムの開催等、 |
|
D.平和構築イニシャティブ |
バングラデシュ政府との対話、関係国際機関への働きかけ |
|
E.ドナー対話 |
バングラデシュ支援ドナー国への働きかけ |
|
F.国際ロビーおよびアドボカシー活動 |
国連機関、人権団体等への働きかけ |
CHT委員会の構成(案)
|
バングラデシュ人メンバー |
|
Mr.Shapan Adnan(シンガポール大学教授) |
|
Ms. Sara Hossain(弁護士) |
|
Mr. Zafar Iqbal(作家) |
|
Ms. Sultana Kamal(弁護士) |
|
国際メンバー |
|
Lord Eric Avebury(英国下院議員) |
|
Ms. Victoria Tauli Corpuz(国連先住民族常設フォーラム議長) |
|
Mr. Kuupik Kleist(グリーンランド国会議員、前デンマークデンマーク国会議員、前イヌイット極地委員会の常務理事) |
|
Ms Ida Nicolasen(文化人類学者、国連先住民族常設フォーラム副議長、国際人権学術社会ネットワーク理事) |
|
Mr. Lee Swepston(元ILO169号条約の起草者) |
|
Mr. Hedeaki Uemura(平和文化スタディ所長、恵泉女学園大学教授、市民外交センター代表) |
|
Ole Henrik Magga(サーミ言語学教授、2002年、2004年国連先住民族常設フォーラム議長) |
|
Robert Evans(欧州議会議員) |
|
Radhika
Coomaraswamy(国連性暴力特別報告員) |
|
Saba Gul Khattak(パキスタン、国際開発政策協会常務理事) |